

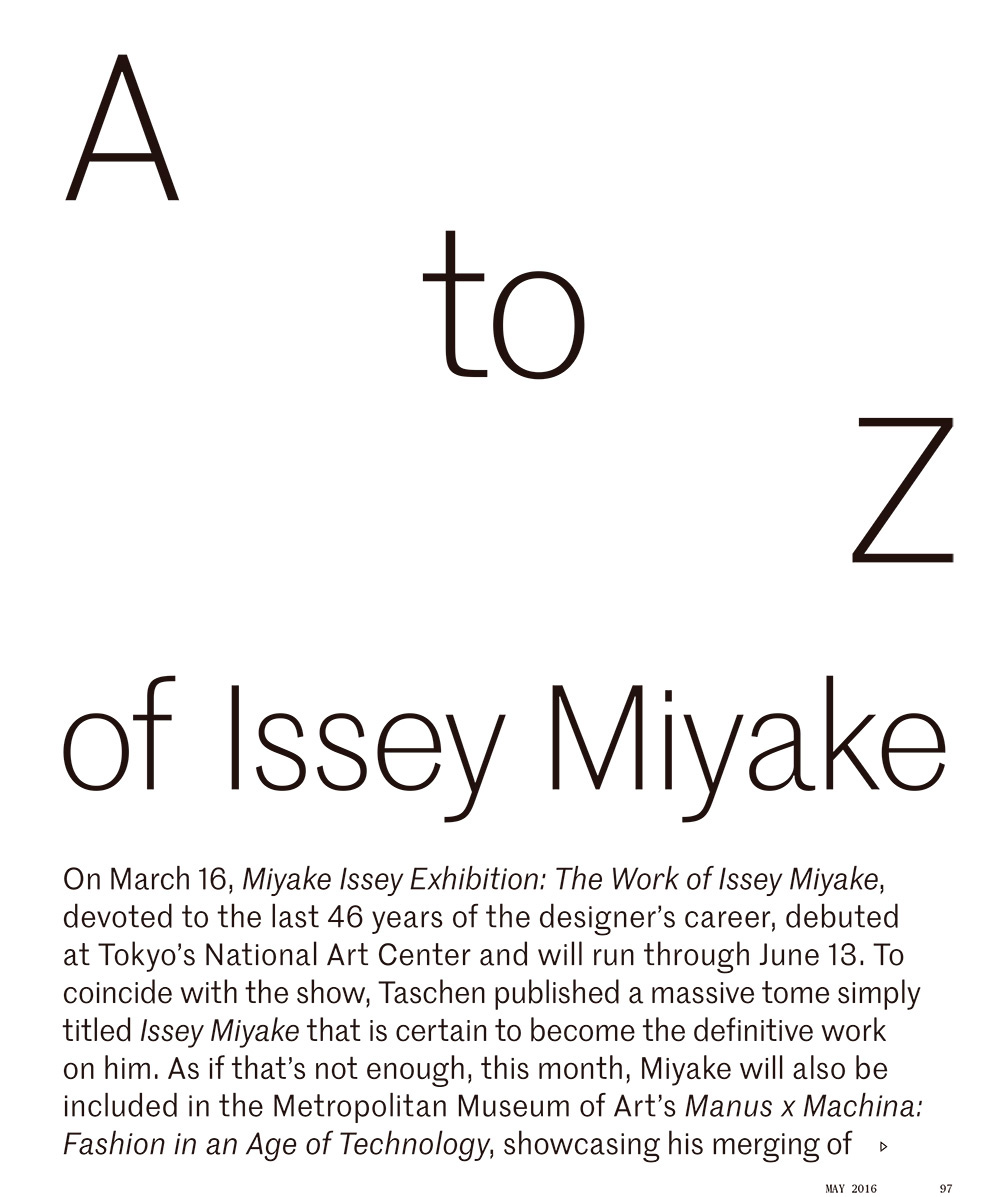
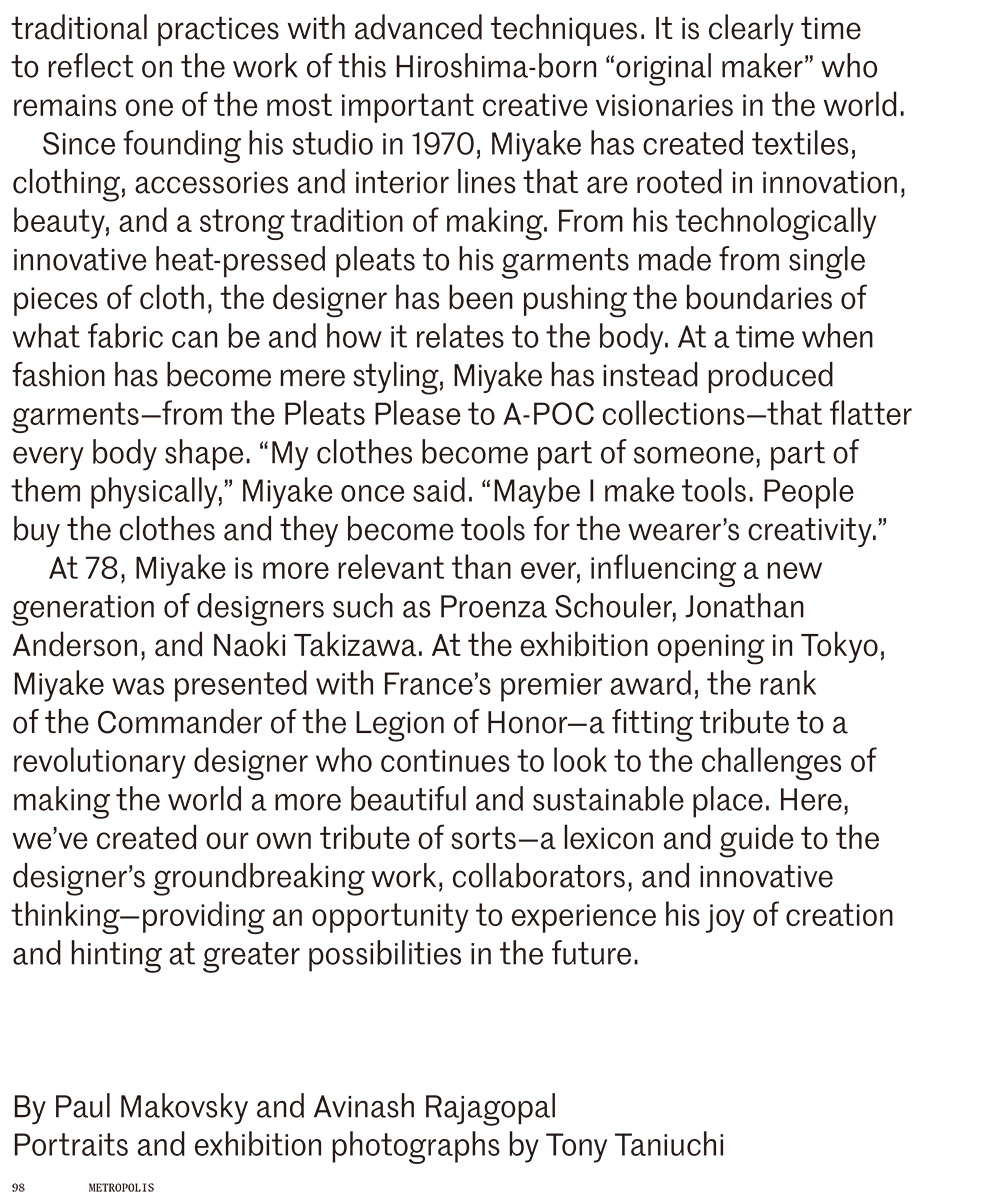
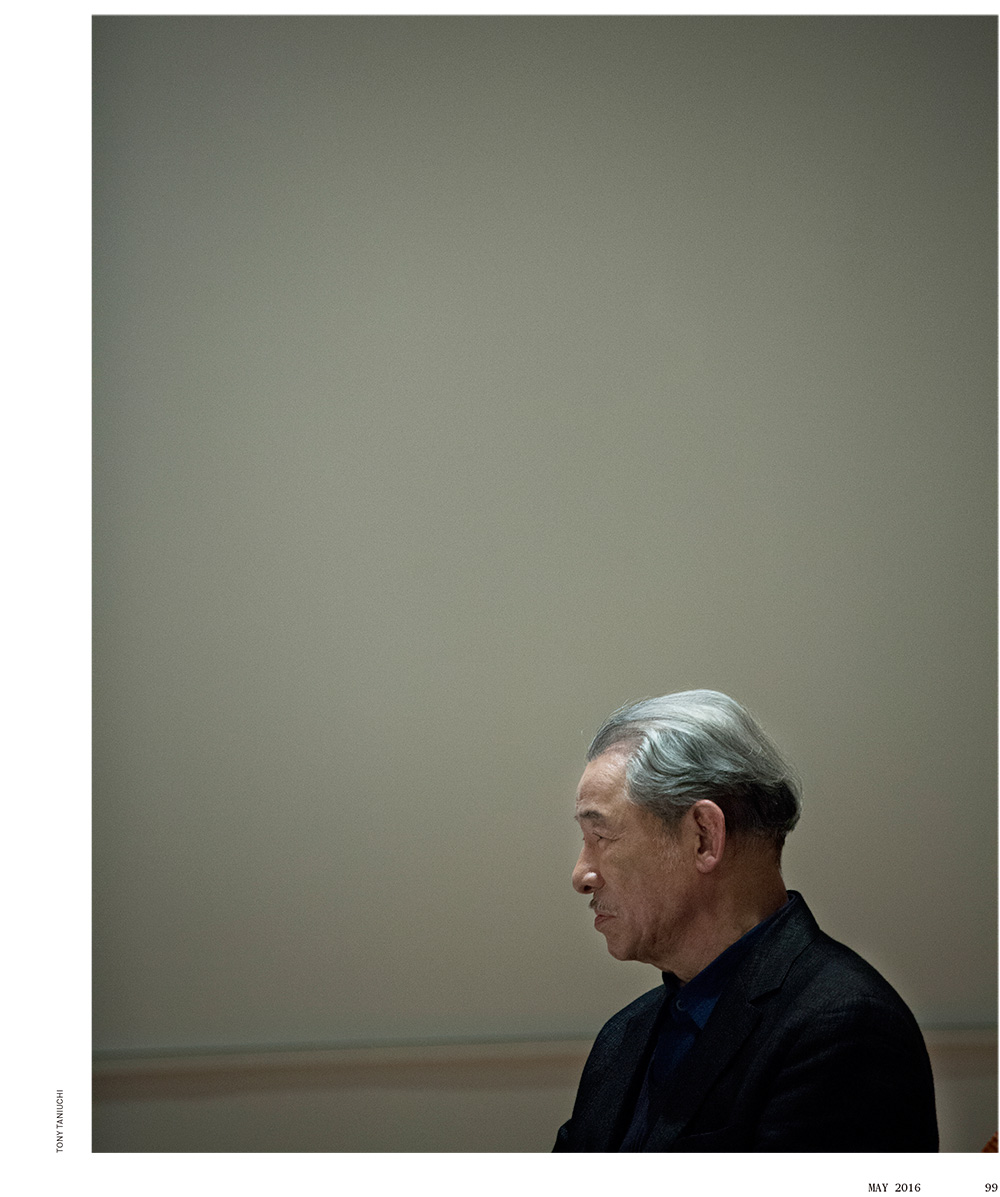









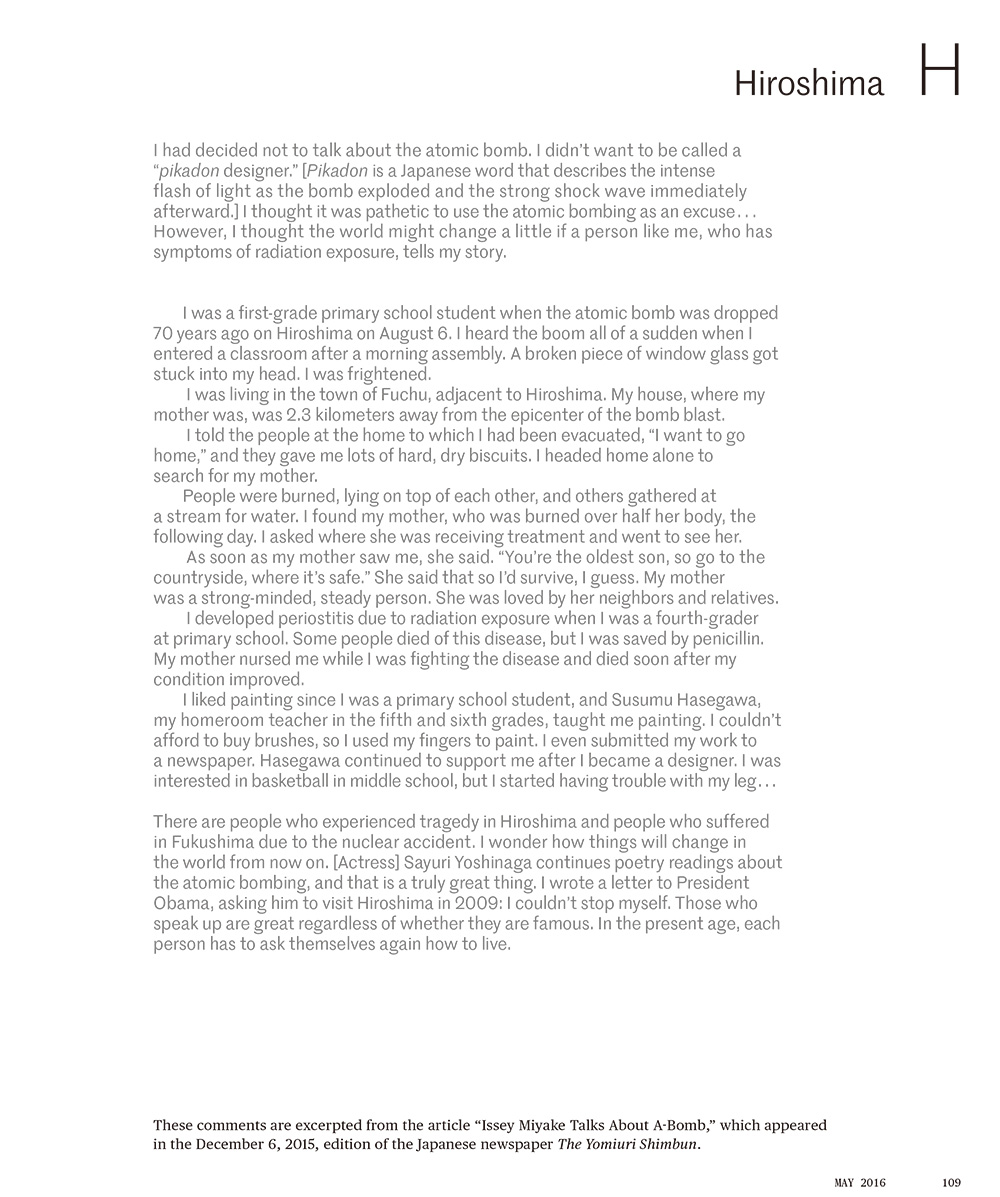













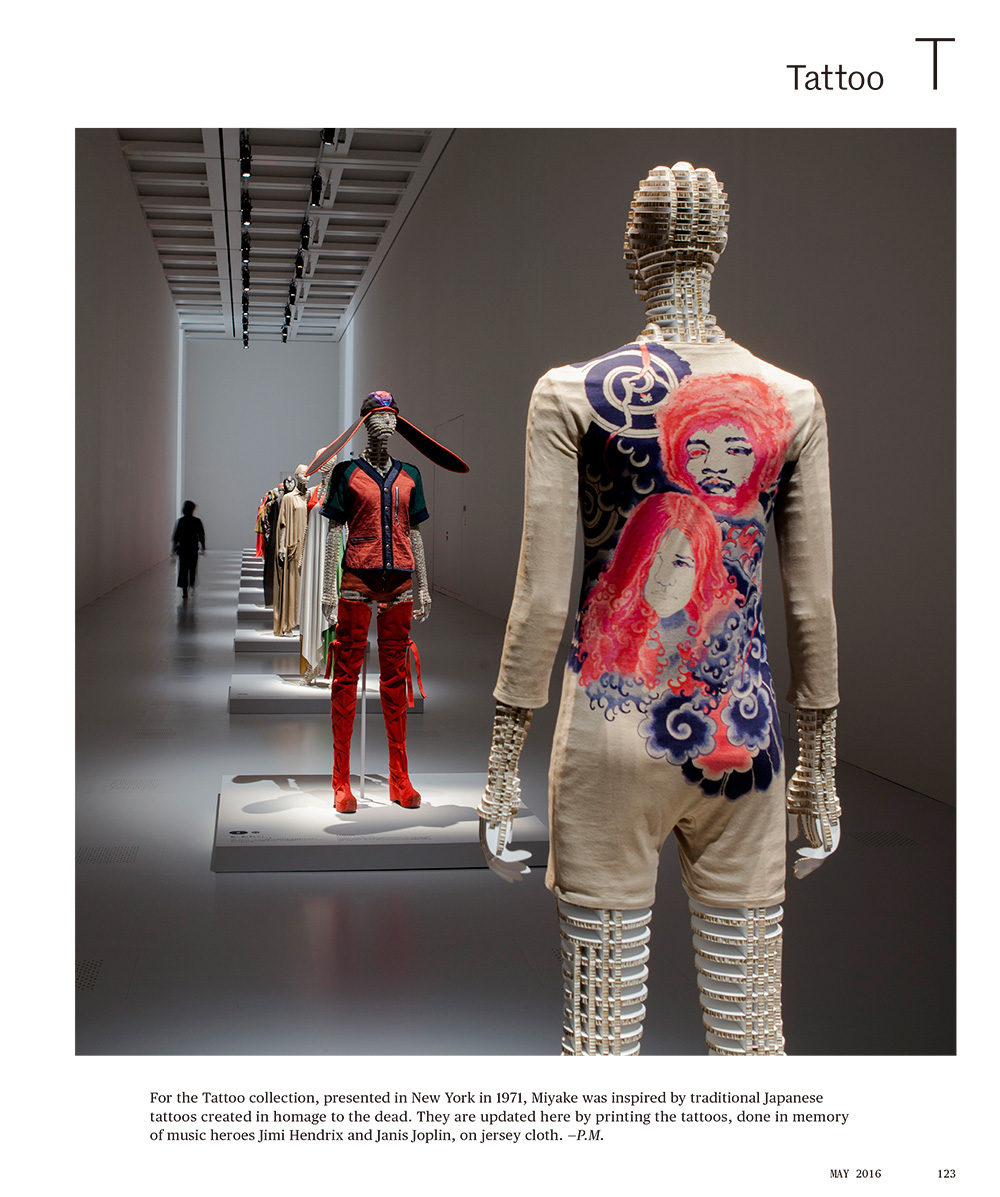










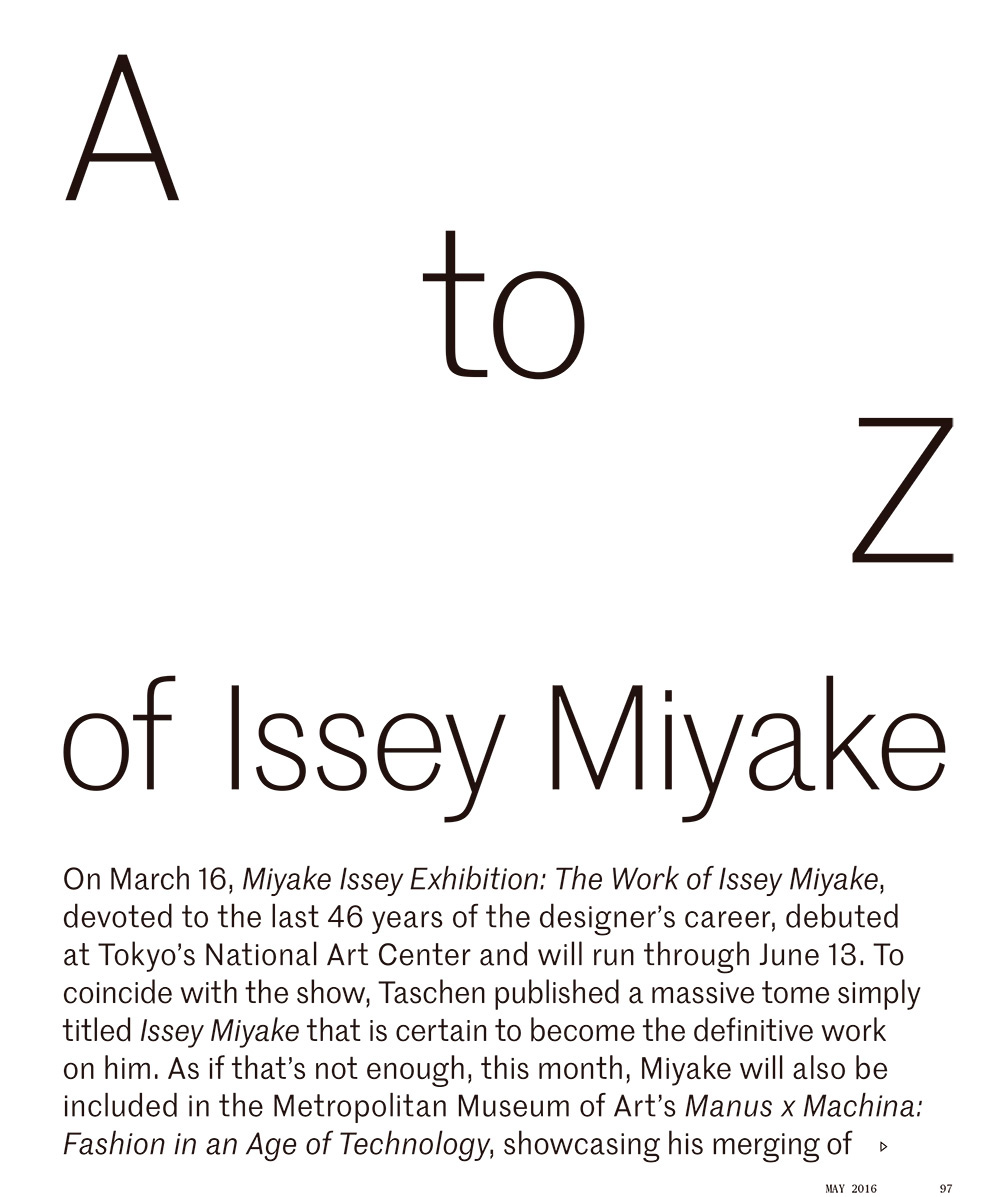
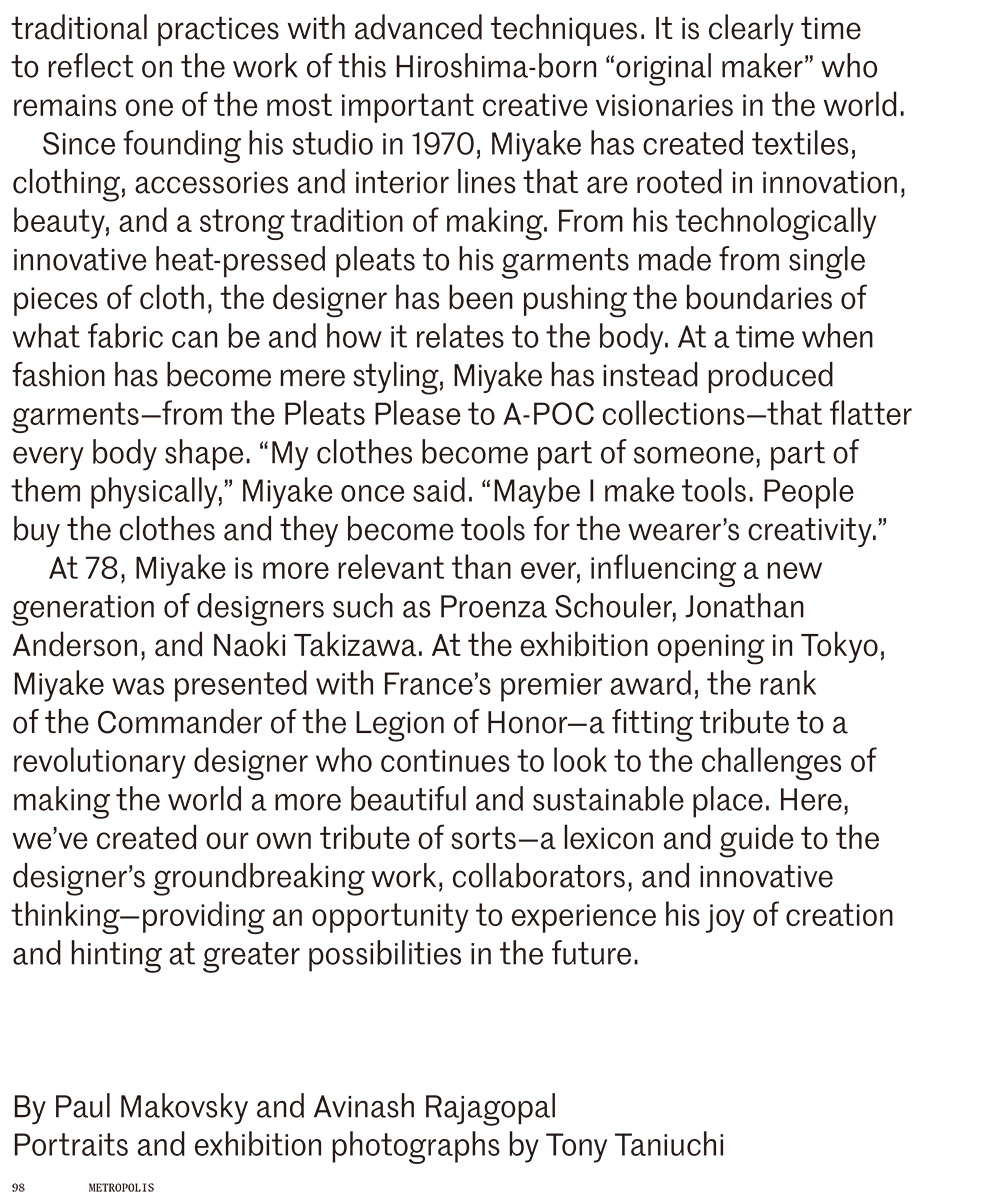
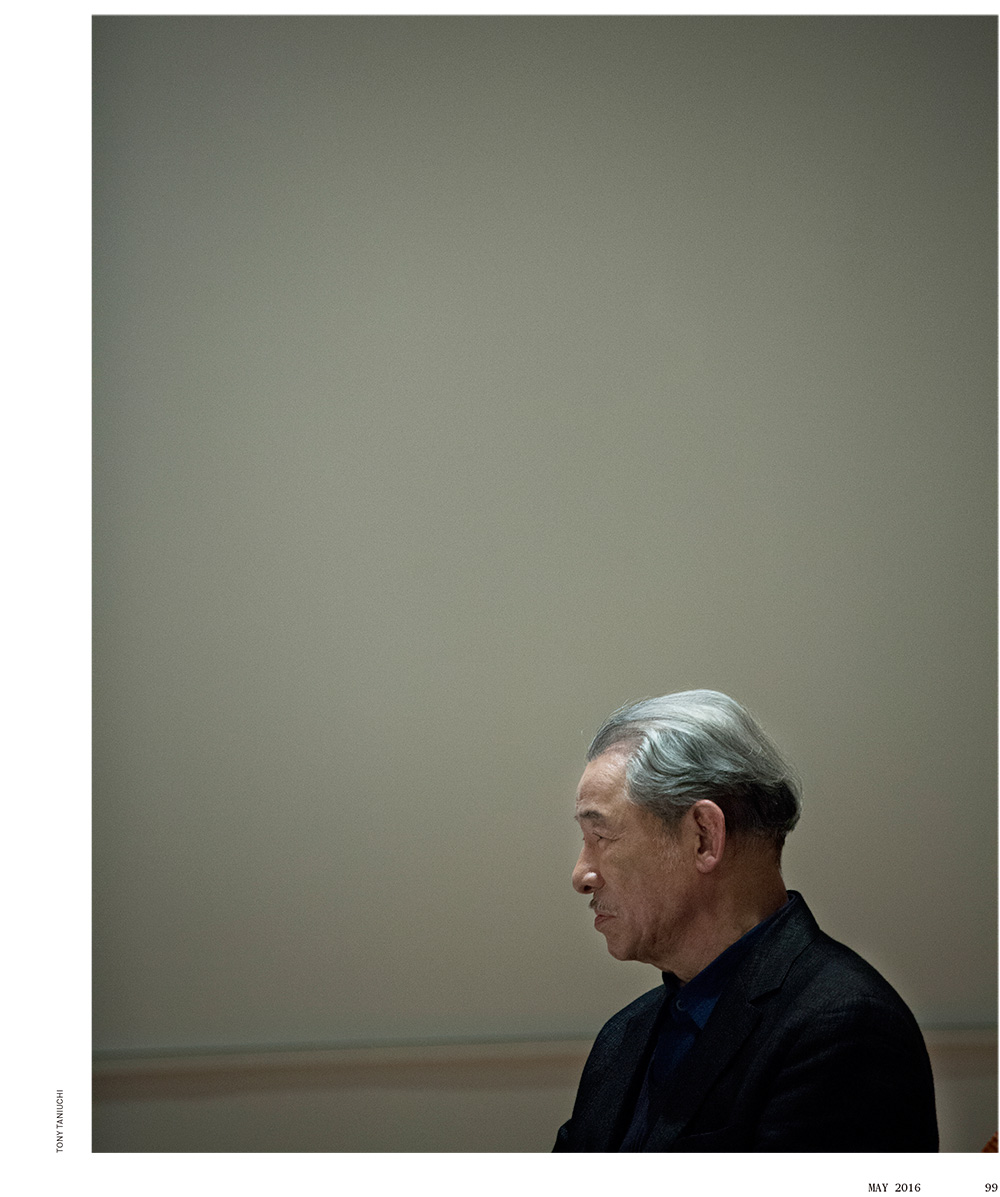









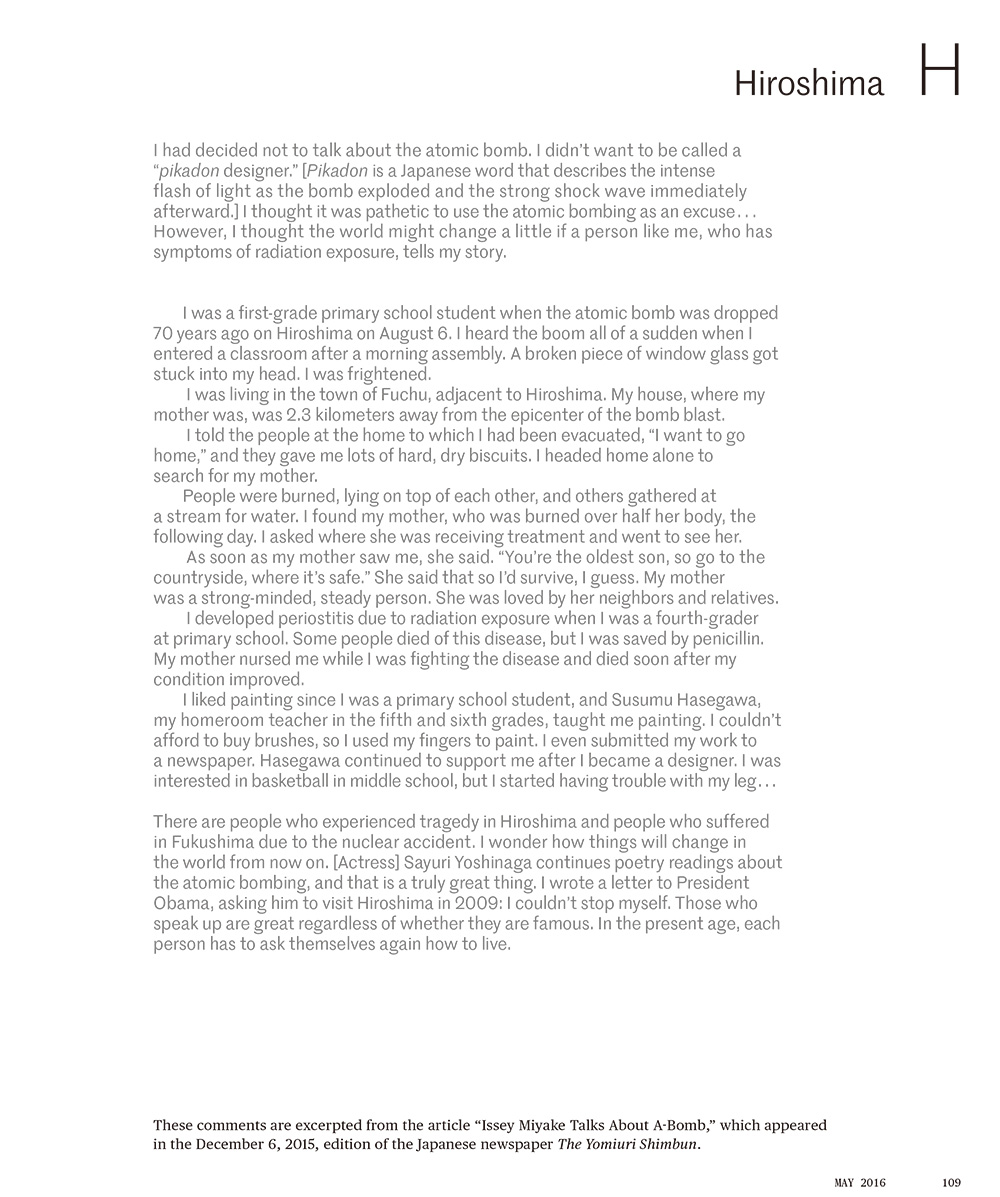













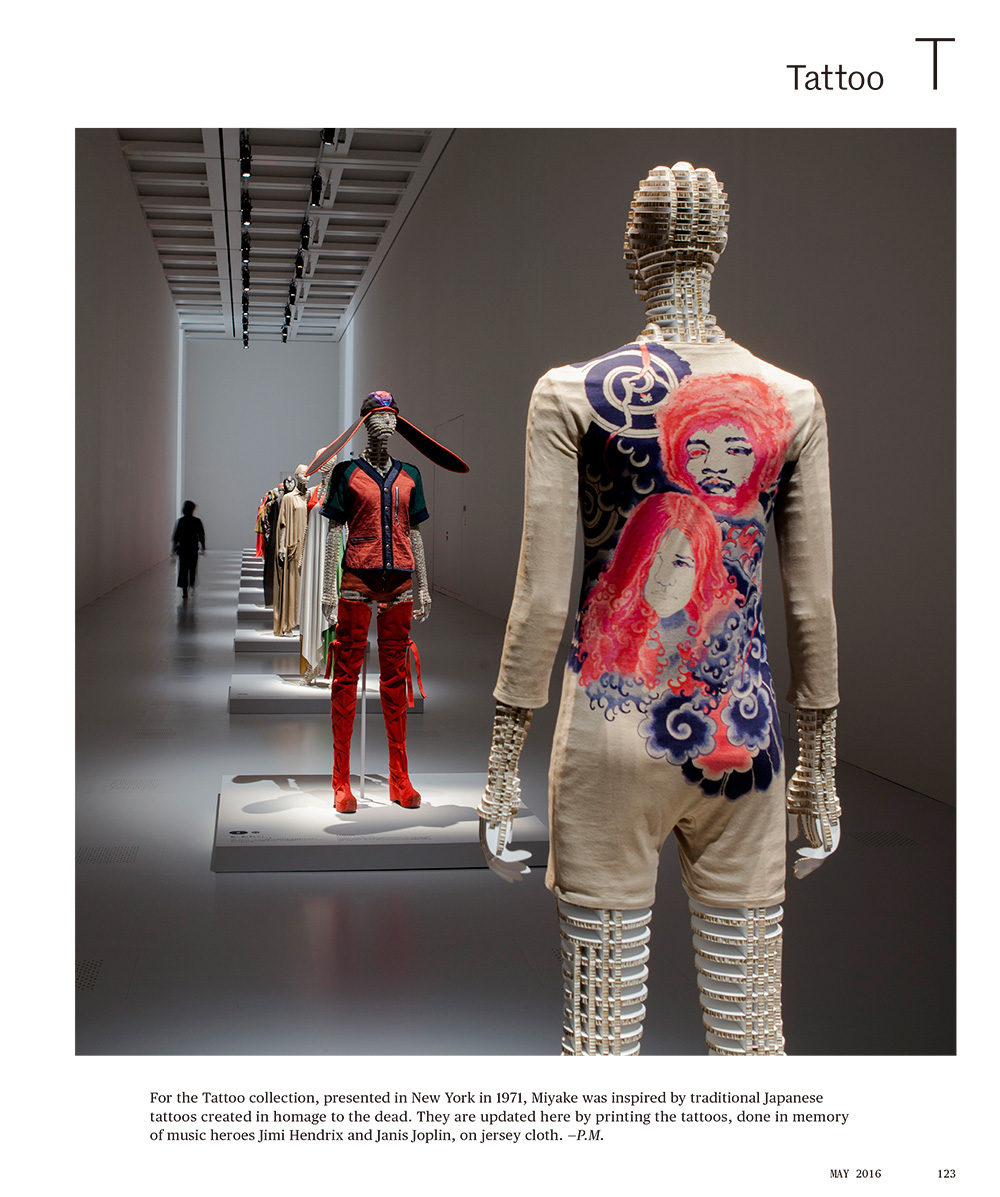






1/18


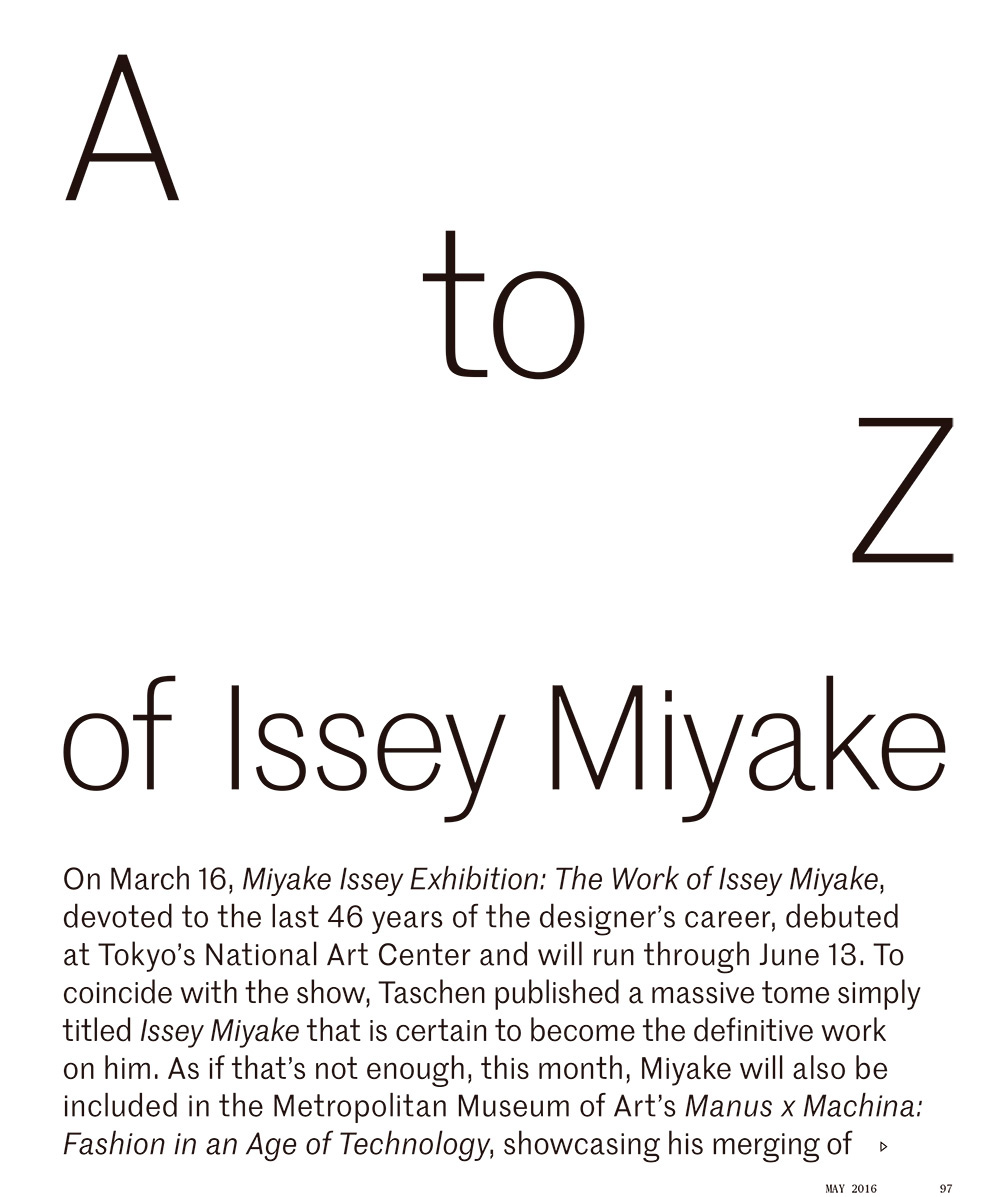
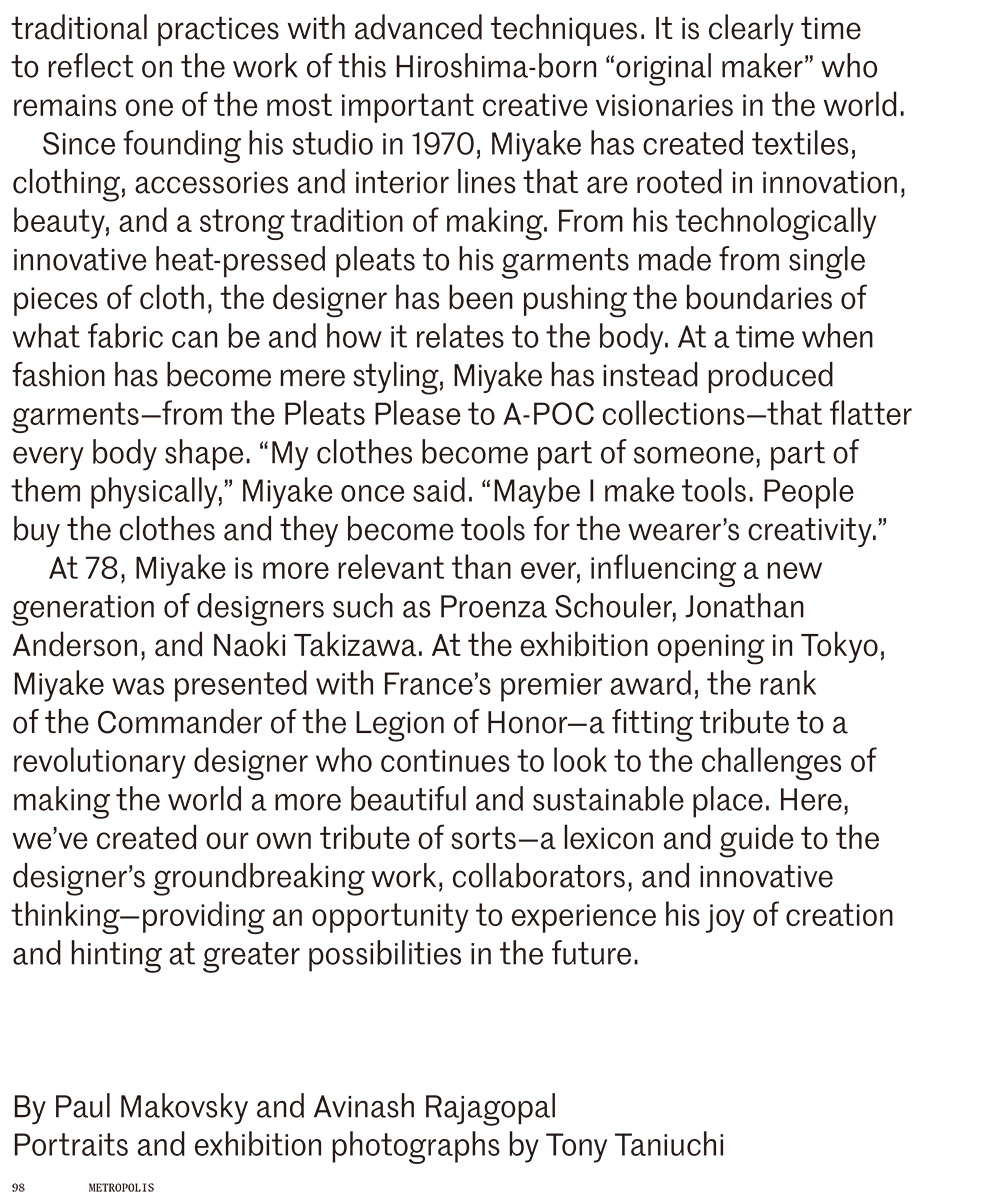
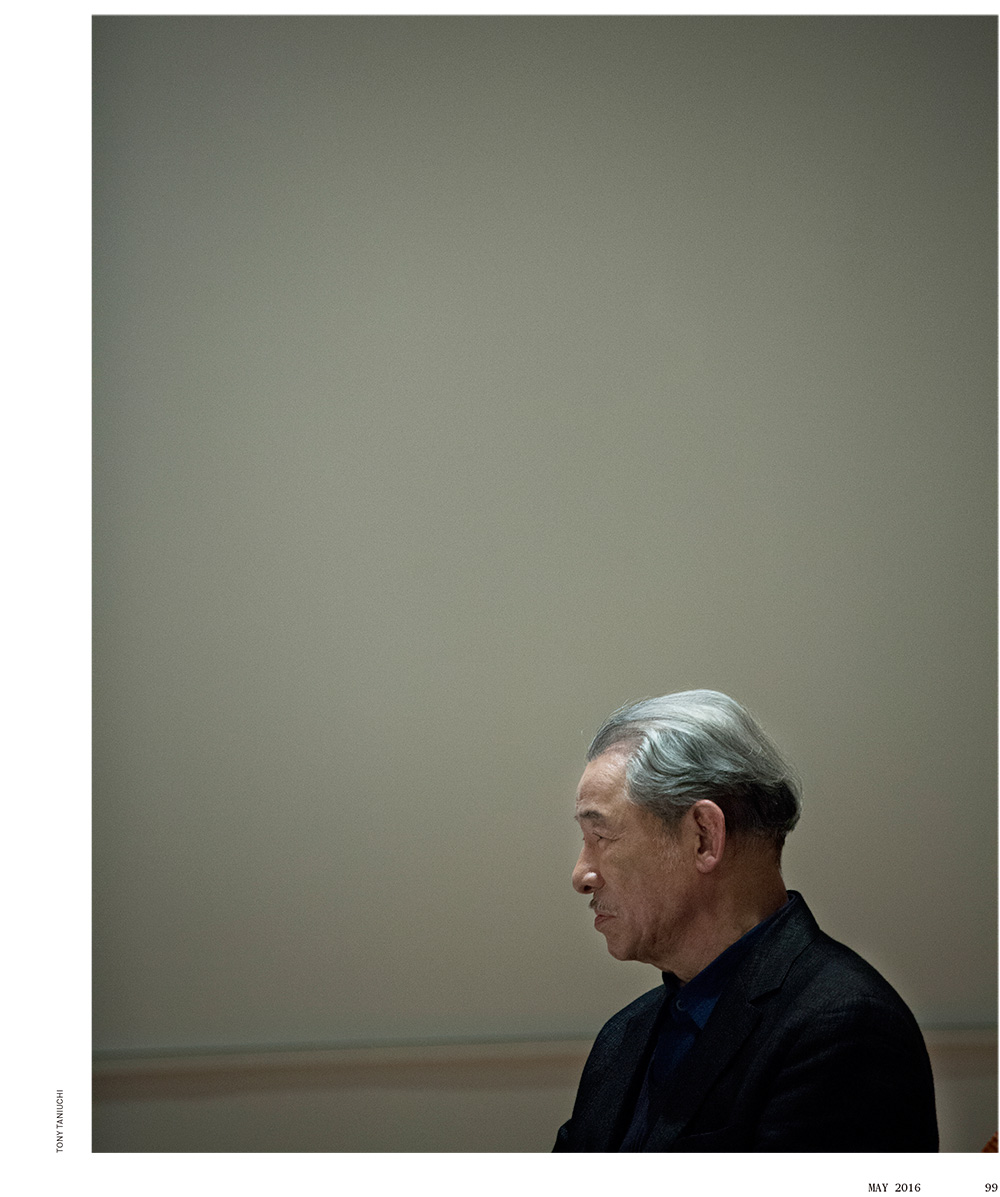
A to Z of Issey Miyake(三宅一生のすべて:三宅一生A to Z)

A
POC(エイポック)

B
Body(ボディ/身体)


C
Collaboration(コラボレーション)

D
Dance(ダンス)

E
East meets West(イースト・ミーツ・ウエスト/東洋と西洋の出会い)


F
Folding(フォールディング/折り)

G
Graphic Design(グラフィックデザイン)
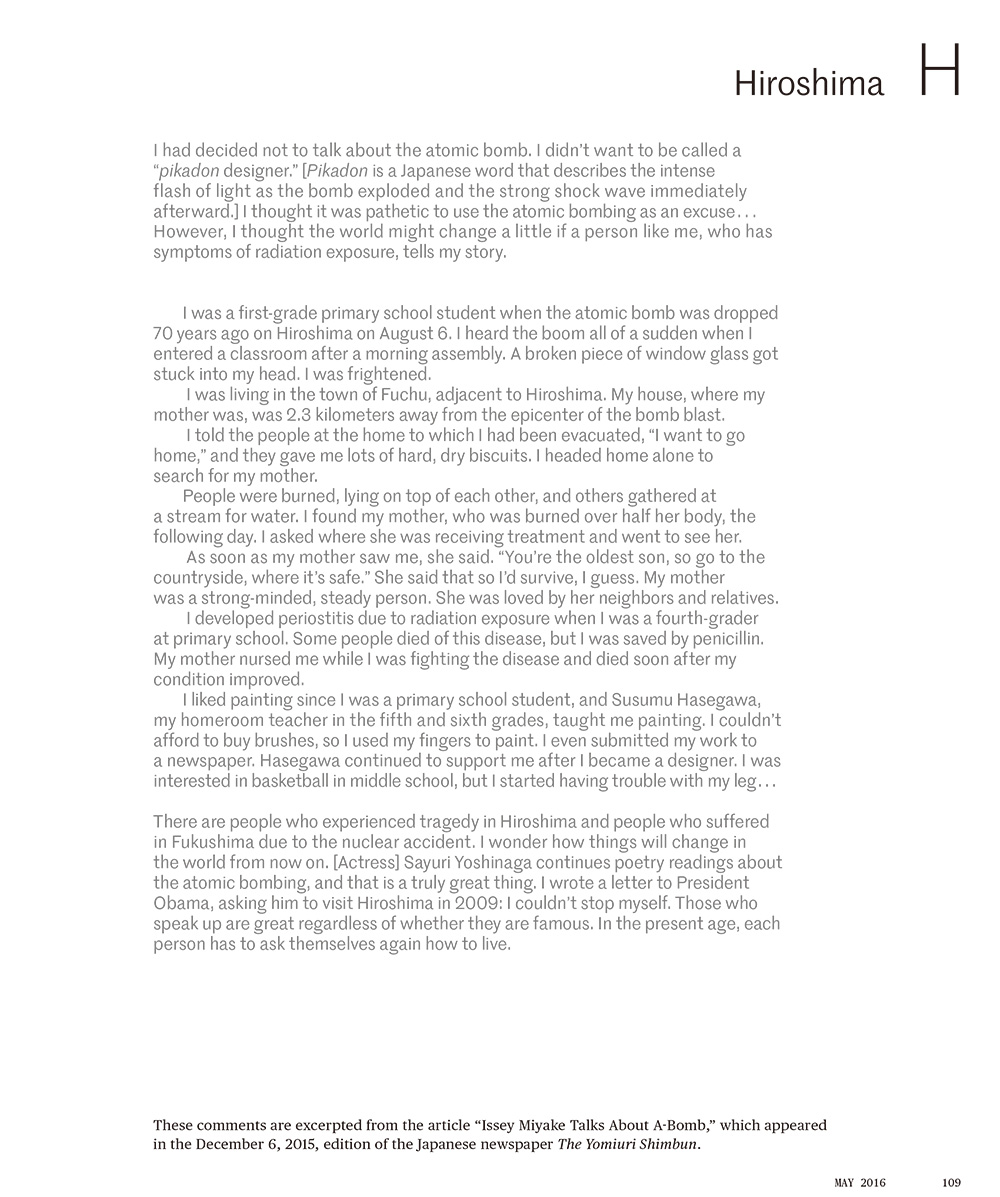
H
Hirosima(ヒロシマ/広島)

I
Irving Penn(アーヴィング・ペン)

J
JOY(ジョイ/喜び)

K
Kuramata(倉俣史朗)

L
Light and Shadow(ライト・アンド・シャドウ/光と陰:陰翳)

M
Material(マテリアル/素材)

N
Noguchi(イサム・ノグチ)


O
Olympics(オリンピック)


P
Pleats(プリーツ)

Q
Quotidian(クォティディアン/日常)

R
Reality Lab.(リアリティ・ラボ)

S
Skin(スキン/皮膚)
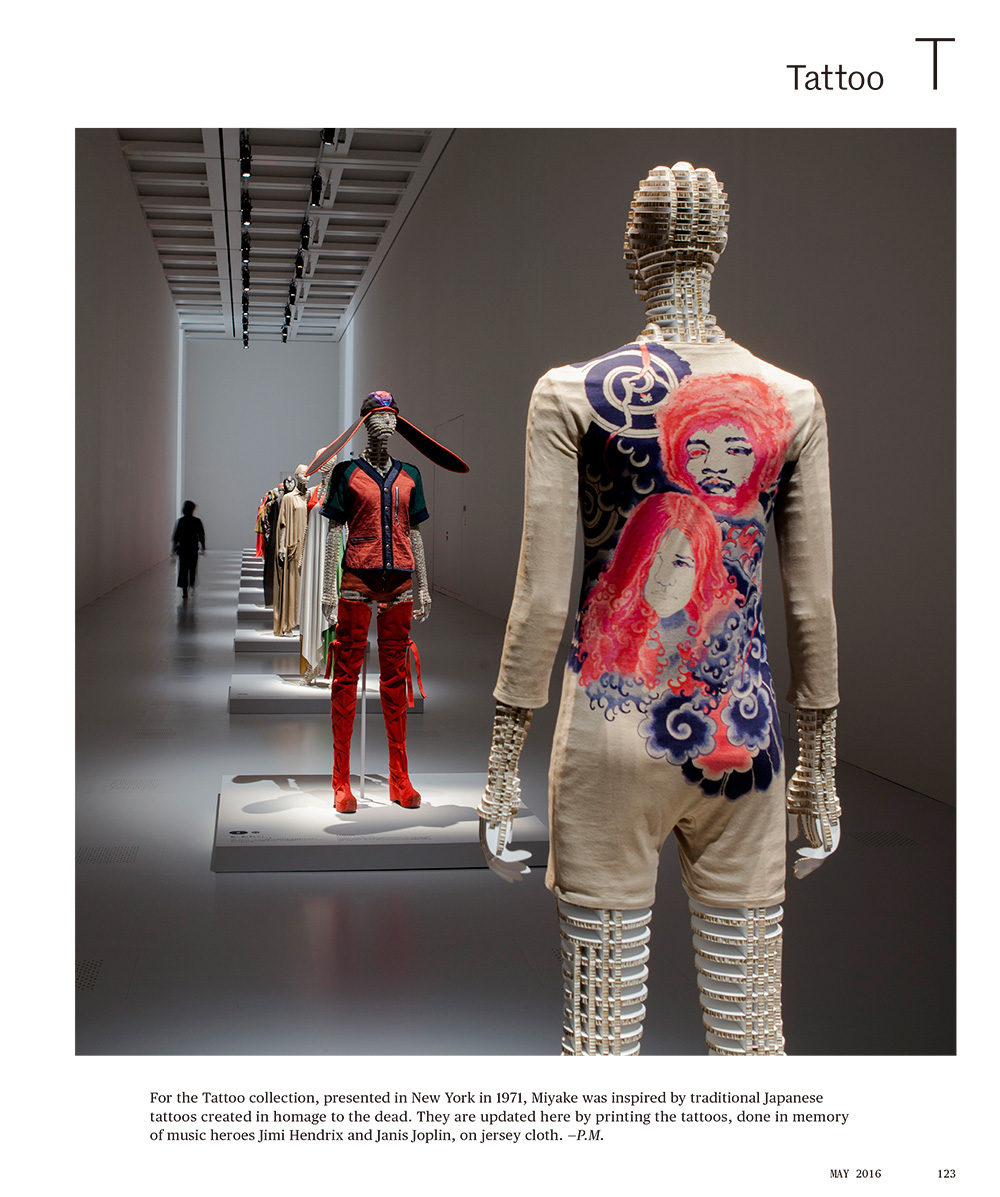
T
Tattoo(タトゥ)

U
UFO(ユーフォー/フライング・ソーサー)

V
Volume(ボリューム/立体)

W
Water(ウォーター/水)

X
XXIc(21世紀)

Y
Yokoo(横尾忠則)

Z
Zoomorphic(ズーモーフィック/動物のかたち)